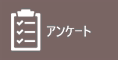能楽師
- Noh Performers

 能を演じる役者
能を演じる役者
-
能に携わる人たちを「能楽師」と言います。
衣装を着て役を演じる「シテ方」「ワキ方」「狂言方(きょうげんかた)」、
謡を合唱する「地謡(じうたい)」、音楽を囃す「囃子方(はやしかた)」、
進行に伴ってさまざまな手助けをする「後見(こうけん)」などで構成されています。
能楽師はシテ方、ワキ方、狂言方、地謡、囃子方のいずれかひとつの専業で、
それぞれに流儀があります。
能が成立した頃、能楽師グループは拠点の地名から「結崎座(ゆうざきざ)」や「円満井座(えんまんいざ)」などと呼ばれており、当時は近畿各地に多くの座があって競い合っていました。江戸時代頃から「座」を「流」と呼ぶようになりました。現在あるシテ方5流のうち、4流は室町時代に大和で興った座で、600年を超えて綿々と継承されています。

- シ テ
-
能では主役をシテと言います。主に仮面をつけて演じられます。
一場面の曲を単式、前場・後場で構成されるものを複式と言い、それぞれの主役を「前シテ」「後シテ」と呼びます。

- ワ キ
-
シテに対する相手役です。現実に生きている男性の役で、能面は使用しません。僧が最も多く、神職や大臣、山伏、旅人、武人などが演じられます。

- ツ レ
-
シテやワキに従って登場する役で、「連れてくる」という意味です。
シテに従う役は「ツレ」、ワキに従う役は「ワキツレ」と言います。複数の人数で登場することも多くあります。
シテ(左)とツレ(右2人)

- 子 方
-
子どもが演じる役です。少年の役以外にも、大人であっても天皇や貴人などの貴い人物の役の場合は、純粋無垢な子どもが演じる場合があります。

- 狂 言
-
狂言を演じる役です。狂言は登場人物が少なく、2〜4人の場合が大半です。狂言においても主役は「シテ」、その他の役を「アド」「小アド」、大勢で登場する役を「立衆」と言います。曲目は少ないですが、囃子が加わることもあります。

シテ(左)とアド(右)

- あいきょうげん
- 間狂言
-
単に「アイ」とも言います。複式の能の前半と後半をつなぐ役で、ワキの問いに答えて物語りをします。また、シテやワキの供や使いの役として登場し、能を面白く盛り上げる役割を担うこともあります。

- はやしかた
- 囃子方
-
笛、小鼓、大鼓、太鼓の4人による演奏です。曲目によっては太鼓が加わらない場合もあります。各楽器の演奏者は専業職になっています。

- こうけん
- 後見
-
能の進行を補助する役です。演能中の作り物や小道具などの出し入れ、舞台上での役者の衣装の着せ替えなどを行います。また、役者に支障が生じた場合は代役を務める重要な役でもあります。

- じうたい
- 地謡
-
6〜10人程で合唱します。シテやワキの代弁をしたり、情景や季節の風景を謡ったり、役の心情・心理を表現したりし、劇の進展を伝えたりします。古代ギリシャ劇の「コロス」に似ています。